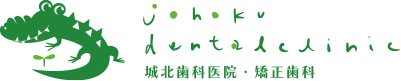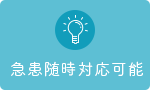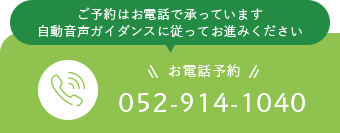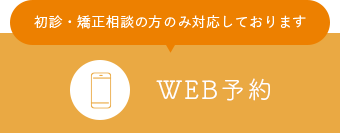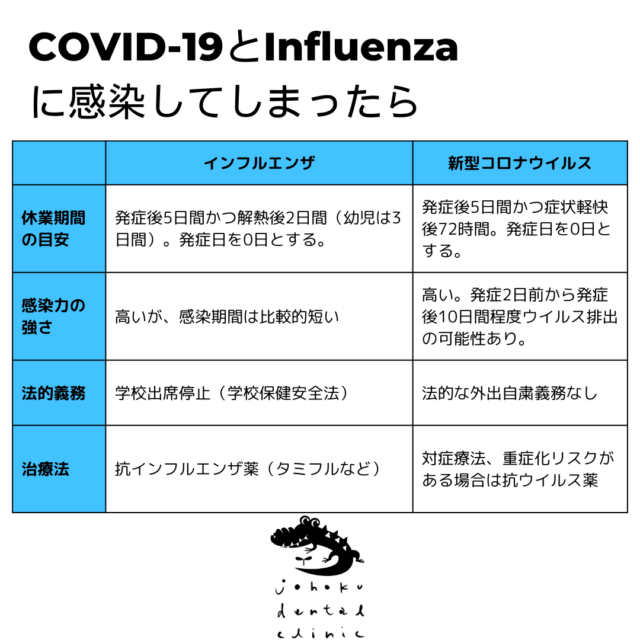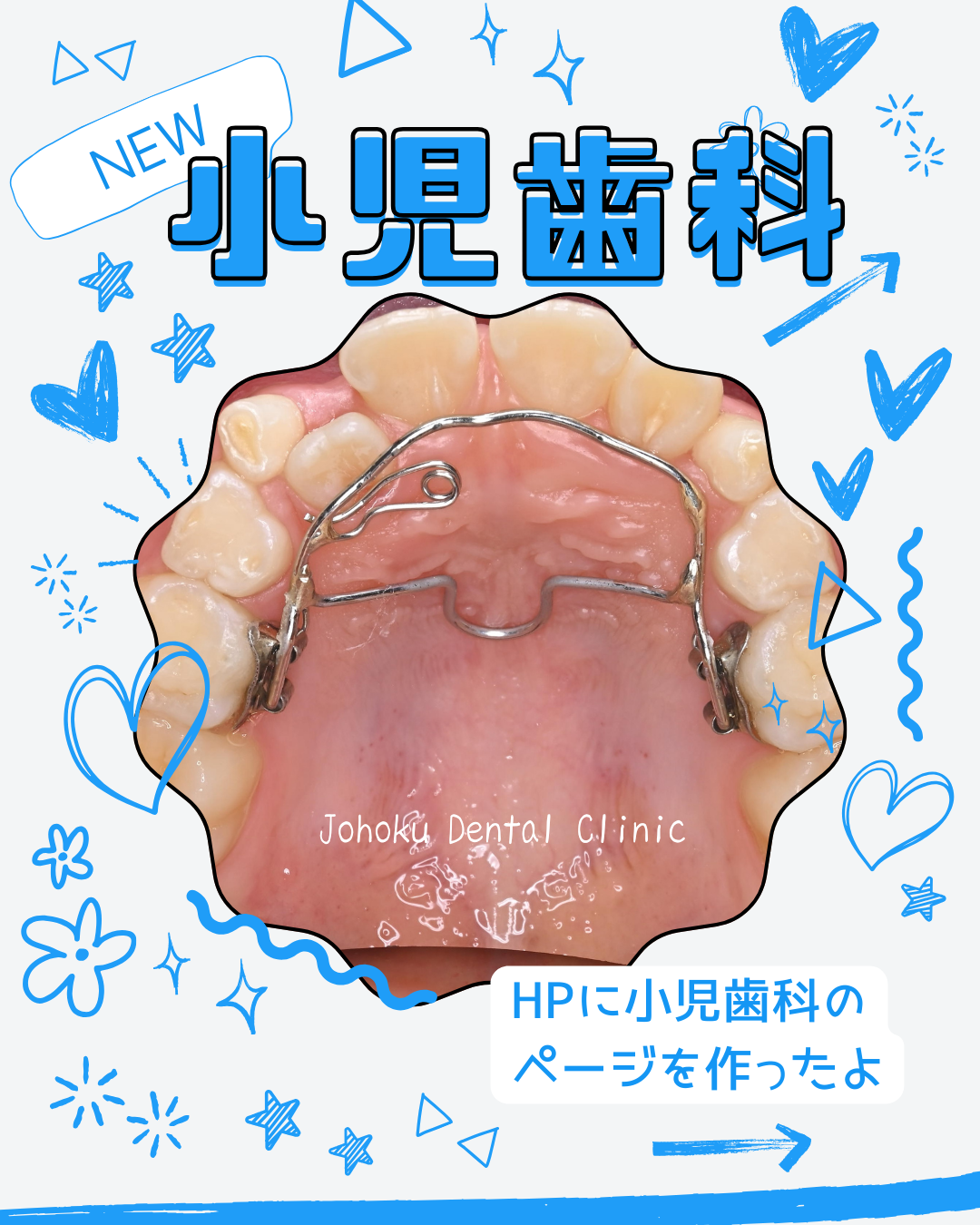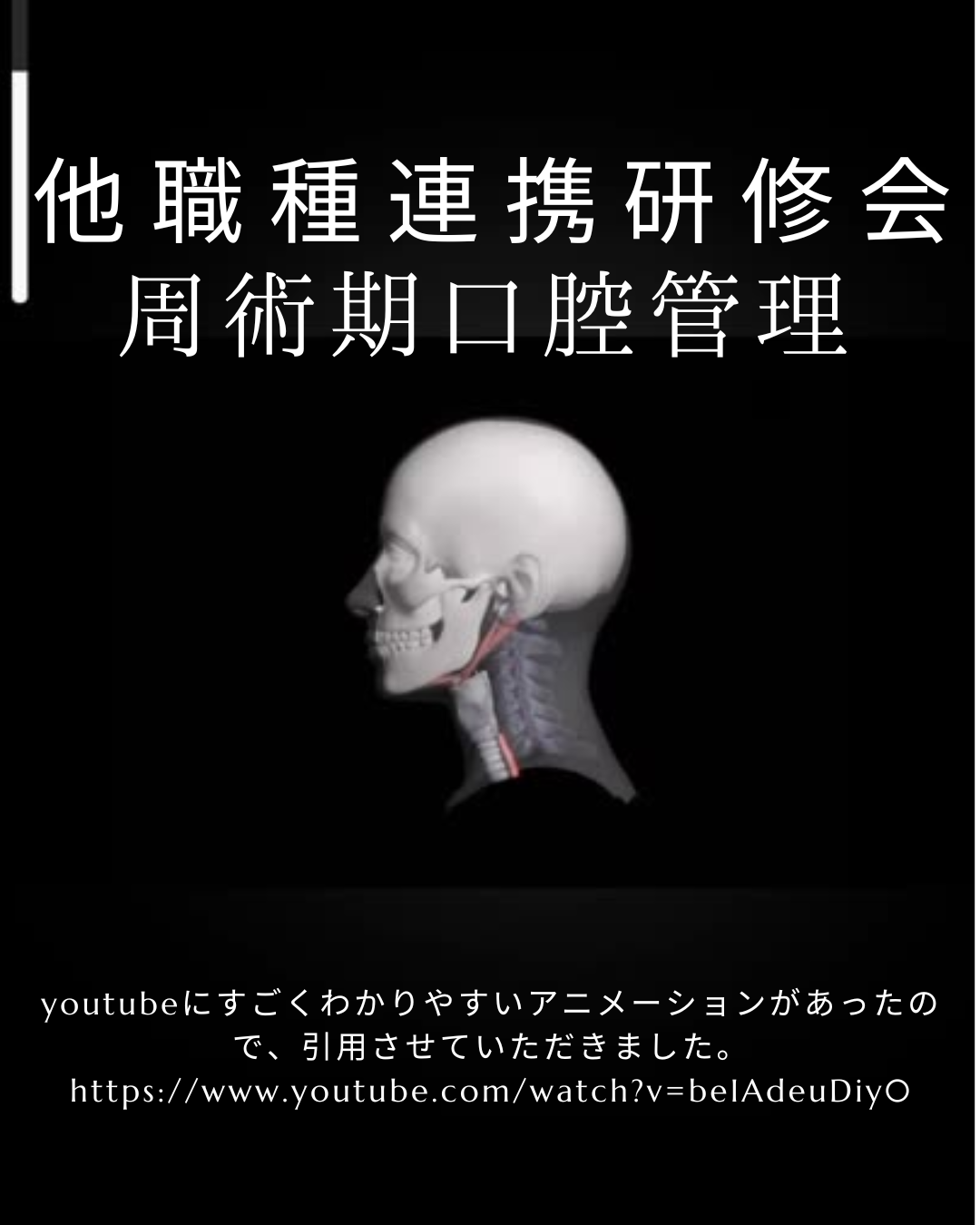「カリフォルニアから来た娘症候群」とは? 〜歯科診療でも起こりうる〜
みなさんは「カリフォルニアから来た娘症候群(The Daughter from California Syndrome)」という言葉をご存じでしょうか? これは、医療現場でしばしば見られる現象で、患者さんの方針や終末期医療について、地元で長く関わってきた家族と主治医が丁寧に話し合い、納得のうえで決定した方針が、遠方から突然現れた娘さんや息子さんによって覆されてしまうという状況を指します。
家族を思う気持ちは一緒なのですが
これまであまり介護や通院に関わってこなかった家族が、突如として登場し、「なぜこんな治療方針にしたのか」「もっと積極的な治療をしてほしい」と強く主張することで、場が混乱してしまう…。罪悪感や親への愛情からの行動であることは理解できますが、すでに築かれてきた信頼関係や医療計画が崩れてしまうのは、非常に残念なことです。
歯科でも起こり得る
これは何も内科や終末期医療に限った話ではありません。私たち歯科医療の現場、特に訪問診療や小児歯科でも、似たような場面が見られます。
たとえば、意思疎通が難しい高齢者の方への訪問診療では、日常的にケアをされているご家族と話し合いながら、現実的かつ穏やかな治療方針を立てていきます。しかし、そこへ久しぶりに会いに来たご家族が突然、「もっとしっかり食べられるようにしてほしい」「(認知症で入れ歯を口に入れることができない状況なのですが)新しい入れ歯を作ってほしい」と強い希望をもってこられることがあります。
また、小さなお子さんの治療においても、普段はお母さんと一緒に来院し、信頼関係のもとで徐々にステップアップしている最中に、滅多に来院されないお父さんや祖父母が突然、「うちの子にはまだ無理」「乳歯を抜くのもかわいそうだ」「フッ素は体に悪いからダメだ」と強い意見を出され、治療の継続が困難になることもあります。
もちろん、家族が大切な人の健康を思って発言することは、とても自然なことです。しかし、医療や歯科治療は「関わる時間」と「信頼の積み重ね」で成り立っています。思いがけない発言や方針転換は、患者さんにとってもストレスになりますし、治療そのものの質を下げてしまうことにもつながりかねません。
大切なこと
私たち医療者は、ご家族と情報を共有しながら進めていくことを大切にしています。大切な家族の治療について意見がある場合は、ぜひ早めに、そして継続的に関わっていただけると建設的な治療方針を組むことができるようになります。「カリフォルニアから来た娘症候群」に陥らないためにも、普段からのコミュニケーションを大切にし、患者さんを中心とした協力体制を築いていけたたよいなと思います。