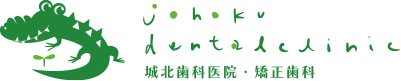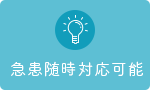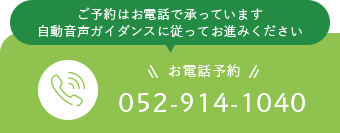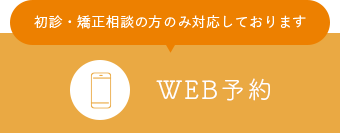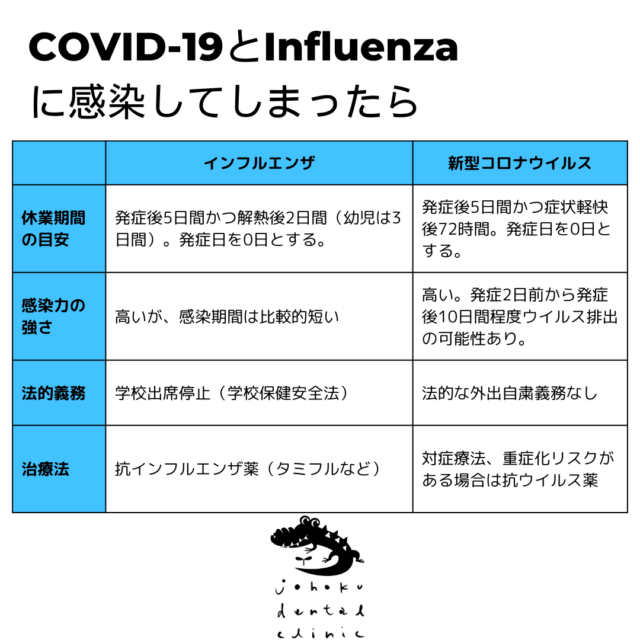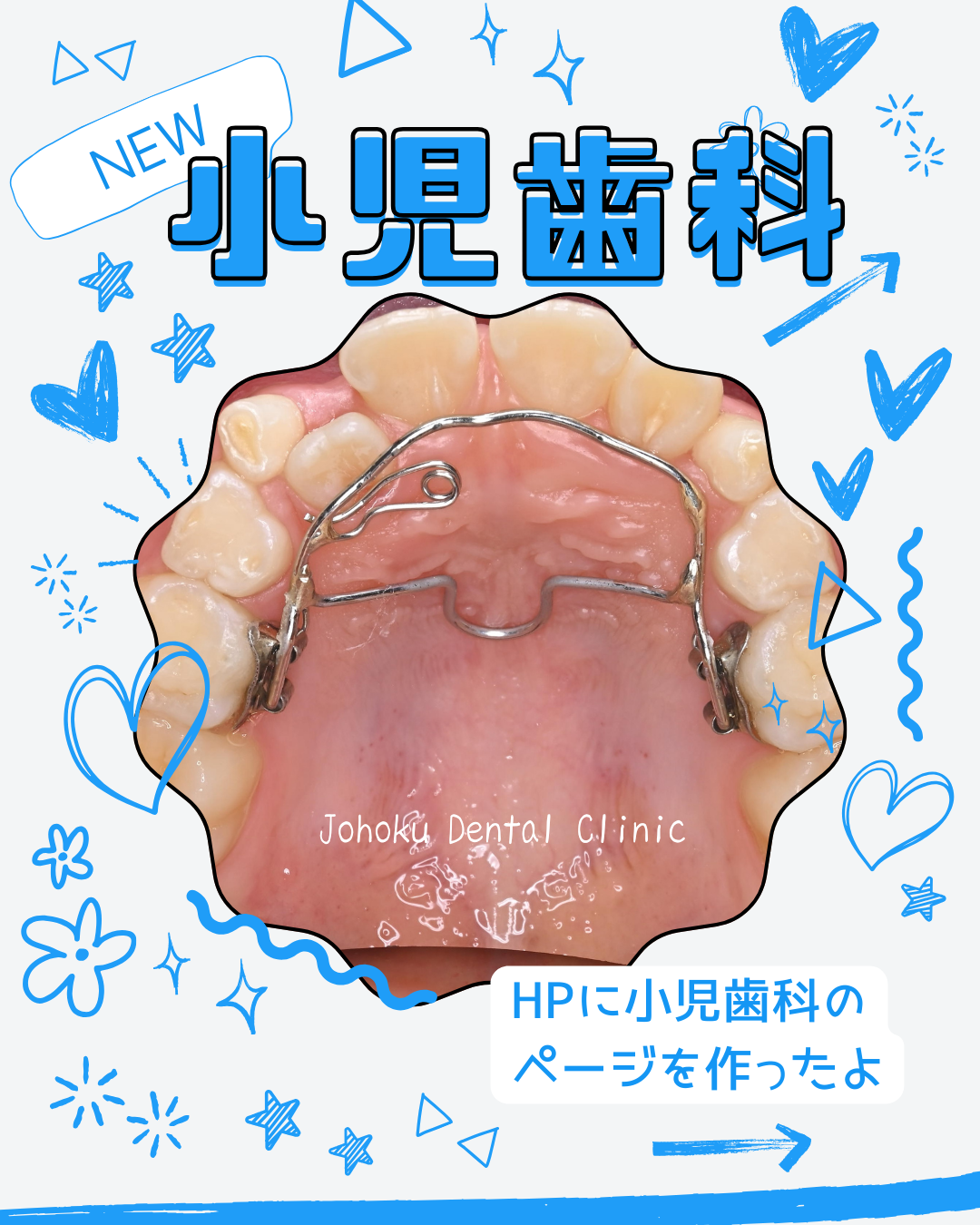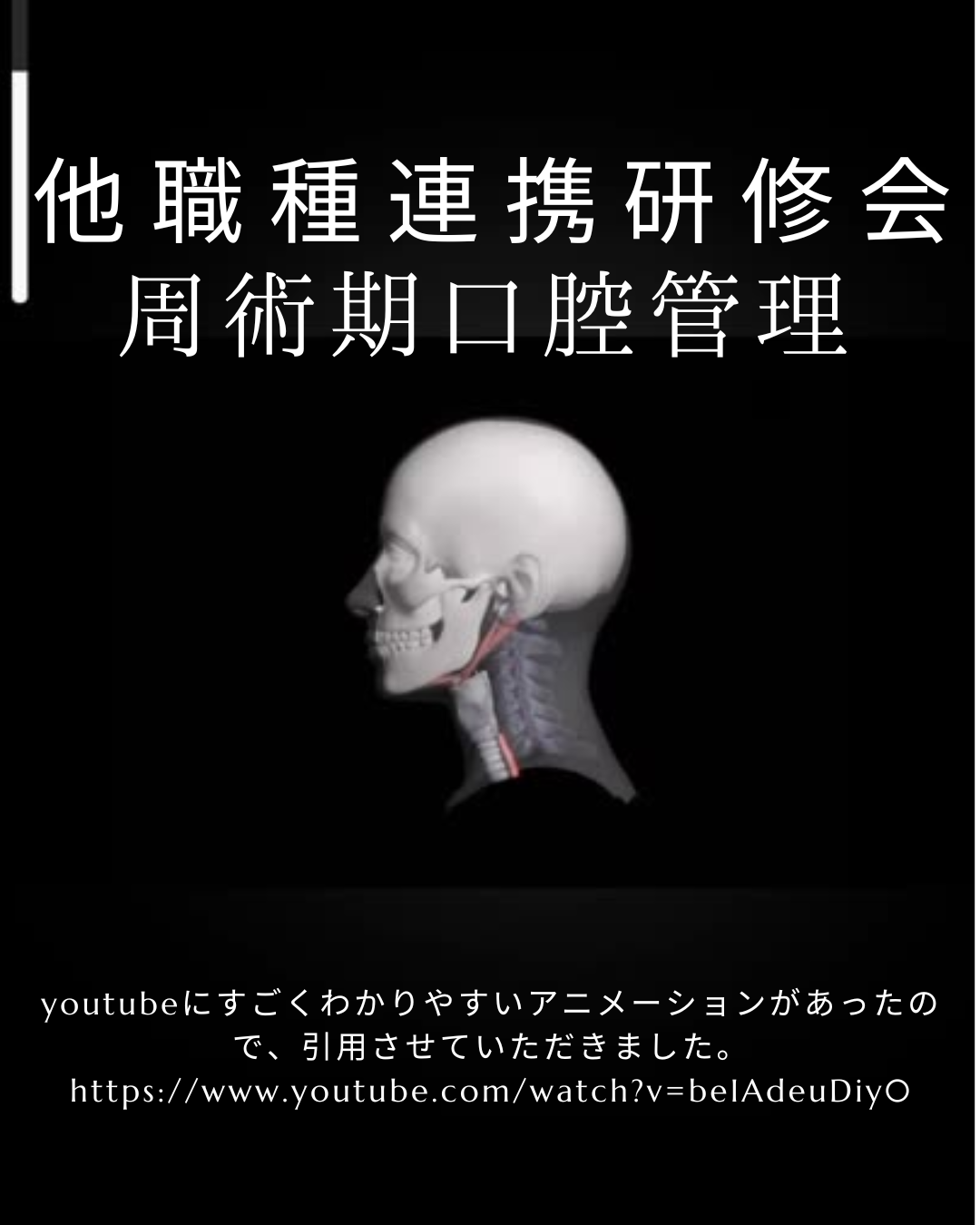たなかたつや展
ミニチュアの世界
「ミニチュア撮影」というくらいの知識しかなく、正直なところ“ミニチュアの世界って面白いよね”くらいに思っていたのですが、実際に足を運んでみるとその考えはガラリと変わりました。まさに「たなかたつや的な発想の世界」に圧倒されたのです。
何かにみたてる
展示のテーマは「見立てる」。身近なものをまるで別の存在に変えてしまう発想力が、とにかくユニークで面白いのです。例えば鉛筆が“たけのこ”に、ドーナツが“病院のレントゲン機器”に。ちょっとしたウィットやシニカルさも感じられ、思わずクスッと笑ってしまいました。作品タイトルもユーモアにあふれていて、まるで言葉遊びを楽しんでいるかのよう。見れば見るほど「なるほど!」と感心してしまいます。
例え話もある種の見立て話?
改めて思ったのは、この「見立てる力」って、とても大切だということです。診療中や事務作業の中でも、ちょっとした工夫や発想の転換が求められることは多々あります。器具の使い方を工夫したり、患者さんへの説明方法を変えてみたり…。例え話が得意な人は、この「見立てる力」がすごいのかもしれません。
日常の中で起きるイレギュラーな出来事に対して、柔軟に対応するのはは、まさに“見立てる力”のおかげなのかもしれません。
なぜミニチュアに惹かれるのかな
それにしても、なぜ私たちはミニチュアにこんなに惹かれるのでしょうか。小さな世界をのぞき込むと、まるで自分の日常を俯瞰する視点を得たような気持ちになります。ガチャガチャやトイカプセルが人気なのも、その心理に近いのかもしれません。普段見慣れた世界が、ちょっと違う角度から見えると、不思議と安心感やワクワク感が生まれるのです。日常を第4人称の視点から見るような、まるで村上春樹の小説の一節に迷い込んだような、不思議な感覚。
たなかたつやさんの作品を通して学んだのは、発想の柔らかさと、物事を楽しく捉える視点の大切さでした。これからも私たちも、患者さんに少しでも安心していただけるように、“見立てる力”を活かしながら日々の診療に取り組んでいきたいと思います。